切削油は金属加工に欠かせない潤滑剤ですが、その使用に伴う環境問題は深刻な課題です。特に、地球環境への負荷と作業者の健康被害の二つの側面から注目されています。切削油やその廃液、スラッジが適切に処理されない場合、水質・土壌・大気汚染を引き起こし、さらに有害物質の含有やオイルミストの発生が作業環境の悪化を招くからです。この記事では、こうした切削油の環境問題とその対策、最新の技術動向について詳しく解説します。
切削油の環境問題には、水質・土壌・大気汚染や有害物質の含有、オイルミストの発生による問題、スラッジの蓄積による問題などがあります。ここでは、それぞれの問題がどのように発生するのかを解説します。
切削油やその廃液、またスラッジ(油と金属粉の混合物)が適切に処理されない場合、水質汚染・土壌汚染・大気汚染などの環境問題を引き起こします。例えば、廃油やスラッジが不法投棄された場合、油成分や有害物質が河川や地下水に流出し、水生生物や飲用水資源に悪影響を及ぼすほか、土壌にも残留して長期的な環境汚染の原因となります。また廃液や油を焼却処理した際には、ダイオキシンや有害ガスが発生することで大気を汚染するリスクも高いです。不適切な処理や排水規制違反は、環境への悪影響を深刻化させます。
従来の切削油には、塩素系化合物やPRTR法で指定された有害物質が含まれていて、これらの燃焼時にはダイオキシンや環境ホルモンの発生リスクがありました。特に塩素化パラフィンなどの塩素系極圧剤は安価で効果的な一方、環境負荷が大きく、塩素ガスや有害化学物質の発生源になっていました。これらの成分は法規制の強化やJIS規格の改正により使用制限が進み、環境負荷の低減を目的に塩素フリーの切削油剤への切り替えが促進されています。また、PRTR対象物質も代替品の開発により削減が進んでおり、現在では環境保全に配慮した切削油の普及が進んでいます。
加工時に発生するオイルミストは、切削油が高速回転する工具や加工物との摩擦で微粒子化し空気中に飛散したものです。このミストは、工場内外の大気環境を汚染し、周辺環境への悪影響をもたらします。オイルミストが設備や電子機器に付着するとショートや故障の原因となり、設備のメンテナンスコスト上昇や機械寿命の短縮につながる悪影響も見逃せません。オイルミストによる空調効率の低下はエネルギー消費の増大とCO₂排出の増加につながり、地球温暖化の一因ともなります。
切削油スラッジとは、金属加工時に発生する微細な金属粉と切削油の混合物で、クーラントタンクなどに蓄積しやすい性質があります。スラッジを放置すると、配管やポンプの詰まりによる機械トラブルや生産停止、クーラント液の冷却性能低下、加工精度の悪化、工具寿命の短縮などの問題が生じます。さらに、スラッジは細菌繁殖や悪臭の原因となり、作業環境を悪化させます。適切に処理されずに廃棄されると、土壌や水質汚染のリスクもあります。工場では定期的な回収・適切な処理が不可欠です。
ここまで切削油の環境問題の発生過程をみてきました。さまざまなリスクがありましたが、近年は有効な対策が取られるようになっています。ここでは、切削油の環境問題の対策について、動向を確認していきましょう。
切削油の環境負荷低減を目的に、塩素フリー・アミンフリー・窒素フリーなどの環境対応型切削油の開発と導入が進んでいます。これらの切削油は、従来の塩素系極圧剤や有害添加物を排除し、人体や自然環境への悪影響を抑制できます。特に植物由来成分の使用や生分解性の向上により、廃棄時の環境負荷も軽減しています。また、切削ミストの発生や刺激臭が少なく、作業環境の安全性向上にも寄与します。
金属加工現場では、環境負荷低減と生産性向上を両立するため、切削油の使用量を大幅に削減する技術が注目されています。代表的な手法が、切削油を使用しないドライ加工と、極微量の切削油をミスト状にして加工点に供給するMQL(Minimal Quantity Lubrication)加工です。MQL加工では従来の加工に比べ、年間切削油使用量を1/20~1/50に減らせるので、廃油・廃液の削減や作業環境の改善に寄与します。また、油の飛散や排水処理の負担が軽減され、機械のエネルギー消費も削減できます。
切削油の廃油やスラッジは、環境汚染や排水規制違反のリスクを避けるため、適切な回収と処理が不可欠です。スラッジ回収装置や濾過・遠心分離などの技術を活用し、クーラント液中の微細な金属粉や油分を効率的に分離・回収する方法が導入されています。回収した廃油やスラッジは汚れや水分を除去し、リサイクルや安全な廃棄処理に回されます。これらの対策により、排水規制への適合はもちろん、廃棄物量の削減や資源の有効活用が進展しています。
切削油の環境問題は、水質や大気・土壌汚染、有害物質の含有、オイルミストの発生、スラッジの蓄積など多岐にわたり、その適切な処理と管理が求められています。近年は塩素フリーやアミンフリーなど環境負荷の低い切削油の開発や、使用量を削減するドライ加工・MQL加工の導入も進んできました。廃油・スラッジの回収・再利用を含む適正処理により環境負荷の軽減に取り組んでいます。このような対策は法規制強化や企業の社会的責任の観点からますます重要となっていて、持続可能なものづくりの推進に欠かせません。
ここでは、生産方式別に切削油(クーラント)を自動供給できる希釈装置を紹介します。自社の生産方式に合わせて適切な装置を導入し、生産性アップ・業務負担の低減・コストダウンを目指しましょう。
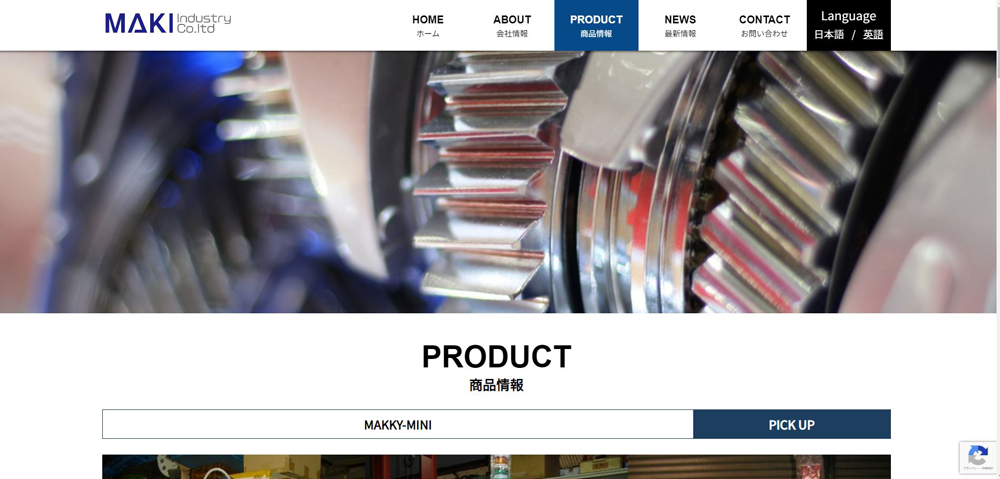
(https://makky.co.jp/product/)
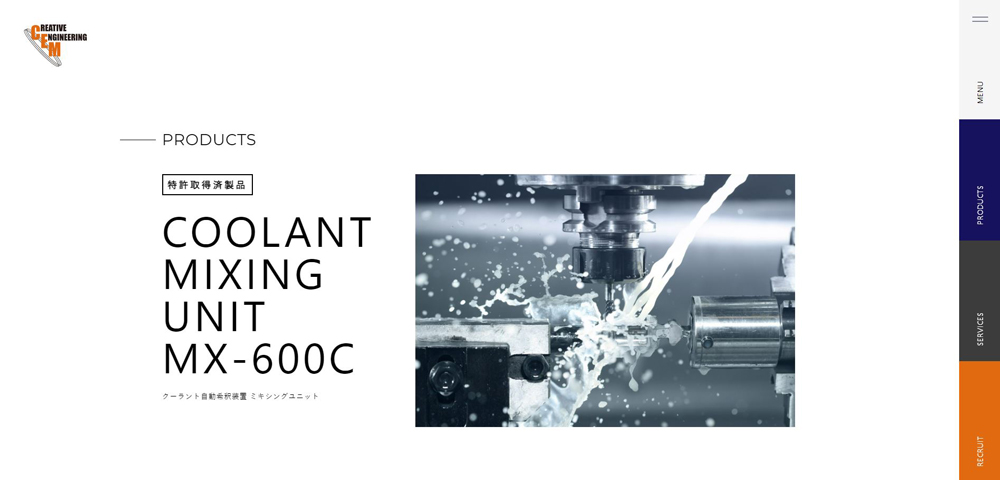
(https://www.kcem.co.jp/product/)

(https://will-fill.com/ja)